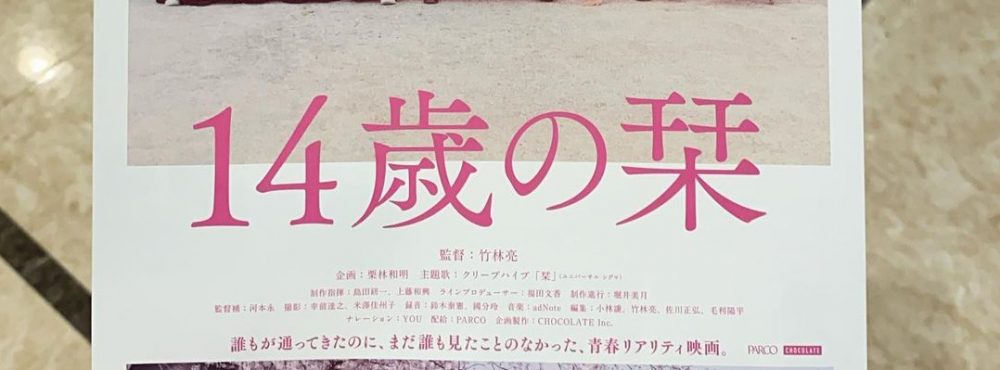14歳の栞という作品を観てきた。
https://www.youtube.com/watch?v=xW0lmC13Jbo
まず思うのは、この作品を新学期前に観ることができて、よかったと思った。
ある中学校の、ある年度の「2年6組」35人の3学期に密着したドキュメンタリー。その密着は、学級内に留まらず、部活や球技大会、家庭や習い事、さらには休日や放課後のプライベートの時間まで。誰かを切り取ってフォーカスするでもなく、視点を教師や親といった誰かに寄せるでもなく、作品自体が、35人それぞれを、一人ひとり見つめている。
いてもたってもいられず、感想を書くためにPCを開けてしまった。これは、Twitterに残すよりも、ブログに「ログ」として残しておきたい。
※ヘッダ画像は、チラシを写メってインスタにアップした画像です。
ドキュメンタリー・映像作品として
実在する中学校の、実在する35人の生徒を、カタカナ表記する配慮があるとはいえ実名で取りあげ、映像に残す。これは、このご時世でとんでもないことだと思う。
入場するときに、更紙の「通信」が配布され、そこではハッシュタグを使って感想を寄せてほしいという文面がある一方、こんなことが書かれている。
この映画に登場する生徒たちは、これからもそれぞれの人生を歩んでいきます。
SNS等を通じての、個人に対するプライバシーの侵害や、ネガティブな感想、誹謗中傷を発言すること
は、ご遠慮ください。どうかご協力をお願い致します。
そしてこのような文言は、映画の最初と最後にも表示される。最後のメッセージには「昨今のインターネット事情をふまえ」という枕詞さえあった。
考えてみれば、「昨今のインターネット事情」があろうとなかろうと、多くの人が観るであろう映画に残る作品として、自分の、あるいは自分の子どもの日常が晒されるということに対して、簡単には同意できないはずだ。この作品は、まず企画としてそれをやってのけた。35人分も、である。
全員が、学校・クラス・部活・放課後の生活など、作品を通じて切り取られる様々な場面に対して、全てをポジティブに捉えているとはいえない。抱える事情は、本当に35人様々だった。それを、ある種赤裸々に映し出している。生徒本人に留まらず、家庭の中での親子やきょうだいとのコミュニケーションも映し出されている。
そして、単に日常を追っかけているだけでなく、35人の個々の独白も採録している。そこでの個別インタビューは、フォーマルな場面においても、インフォーマルな場面においても、どちらでも発生している。そして、インタビュー内容は、対象となる生徒本人についてだけでなく、その本人と関係する生徒についてのことも質問されている場面もあった。
教室で見せる姿、部活で見せる姿、インタビューで見せる姿、それぞれの側面があるなかで、インタビューでは本音も登場した。その本音は、場合によっては他の生徒が知らないであろう側面を映し出す部分もあったと思う。何がすごいって、撮影クルーたちが、生徒たちのそうした本音を引き出すだけの関係性を構築した、というところだ。家庭への密着、休みの日への密着。そうしたことを可能にした関係性構築が、作品の「凄さ」の一つのポイントだと思う。
120分で、35人全員を取り上げている。その順番は出席番号順ではない。35人それぞれが、それぞれに何らかの関係性の糸のようなものを持っていて、それをたぐるように順々に取り上げられていく。Twitterで他の人の感想を見ている時に「カット割が多くて、創り手のこだわりが見えた」と書いていた人がいたが、確かにその通りで、一人ひとりの抱えている「もろもろ」について、あらゆる角度から取り上げていた。
一人ひとりの様相が、教室で・部活で・帰り道で・家庭で・習い事で・休みの日で、それぞれに違って映る。そこに、独白による本音(いや、本音ではないのかも知れない)が加わることで、14歳として生きることが、決してシンプルでないということを表していて、そして「そうだよね、色々あるよね」という共感と、「だからこそ支えたい」という作り手の願いのようなものを、編集から感じることができた。
作品説明にあるように、たしかに劇的なドラマはなかった。しかし、造られた物語以上に、ドラマ性を感じることができた。その意味で、「傑作」の名にふさわしいドキュメンタリーだと感じた。その意味で、この企画を実現にまで持っていった製作陣と、この密着に協力をした全ての人々、特に35人の生徒たちに、拍手を送りたい。
ちなみに、おそらくだが現時点において、登場した生徒たちは最低でも新年度に高校2年生を迎え、それぞれの道を進んでいるはずである。封切り後に生徒たちがこれを見て、どのようなことを感じたのかを、聞いてみたい気もしている。
中学2年生の副担任をしていた視点から
35人の生徒たちが、一人ひとり、抱いていることが違っていて、見せる様相が教室・部活・帰り道・家庭・休日で違っていて、一丸でもなければ一様でもないという感じを見受けたとき、私は、自分の仕事において接している生徒たちに対して、申し訳なさを覚えてしまった。
そうだよね、いろいろあるよね。クラスのメンバーに対して、それぞれが思うことも様々だよね。クラスが楽しいと感じている人もいれば、どこか冷めたスタンスを取る人もいるよね。全員と楽しく過ごしたいと思う人もいれば、関係性を持つことをめんどくさいと思う人もいるよね。
ある側面では「調子に乗っている」と見られる行動も、実はそれがコミュニケーションの道具だったりするよね。一方で、「ぼっち」みたいな印象に映っている人も、本当はコミュニケーションを取りたいと思ったりしているよね。周りからの見え方を気にすることもあれば、逆にそれを気にしないってこともあるよね。
将来の見通しに対して、本音と建前を使い分けることもあるし、そもそも見通しが持てないってこともあるよね。自分のことが嫌いだって思ったり、自信がないって思ったりすることもあるよね。変化をしようとする人もいれば、変化をするタイミングを逸したという人もいるよね。
そんな、生徒たちの抱く「もろもろ」は、生徒一人ひとりによってバラバラで、そしてそれは決して、教室空間のなかで見える様子だけでは見通せない。
僕は、14歳という、ゆらぎやまよいのある世代に対して、寄り添うというか、そばにいるというか、支えになるというか、あるいは時に引っ張り上げるというか、そういう存在でありたいと思っているところがある。しかしそれは、傲慢だと思った。「だよね」といって受容できたとしても、その受容が、生徒たち本人にとっての何になるというのだろう。
そして百歩譲って、その受容に何かしらの意味があるとして、生徒全員に対して意味をもたらせるかと言えば、それは無理だということにも思い至ってしまった。なぜなら、僕が仕事を通じて見ることができる生徒たちの側面は、かなり限定的である。別言すれば、僕はかなり一側面的にしか、生徒たちを理解していない。いや、本当の理解なんてできていないのかもしれない。
私が抱いた申し訳なさというのは、一側面的に判断をしてしまっているということへの気づきであり、またその「申し訳なさ」の対極にある自分の理想というのは、なんというか「彼らと仲間になる」ことなのかも知れないと気づいた。たぶん、そうはなれないはずなのに。
でも、自分が「仲間の一員」になれなくても、あるいはならなくても、きっと「いきいきといきる」ことは可能なんだろうな、と思った部分もあった。作中で担任の先生が
信用します。信頼します。期待をします。
教員ってそういうもんだから。
と言っていたが、まさしくそこに尽きるんだろうと思った。
その信用や信頼や期待を、受け取る人もいれば受け取らない人もいて、それでも一つ確かなこととして、全員が一人の人間として、もやもやを抱えながらも生きるということができる、それだけ自分を見つめ・周りを見つめ、過去や未来を見つめ、ということが、14歳という年齢にはできている、ということに気づかされた。教員が、なにかをしつらえることで、それが増幅する可能性があるにせよ、それを取ろうと取らまいと、彼らは生きていけるんだ、という見方を持つことは、もしかすると自分に欠けていたかも知れない。
そうなったとき、僕はあるシーンが気になった。それは、担任が用意した、1年間のクラスの写真スライドショー。それを見ている時の教室内の個々の顔つきは、全員が笑顔ではなかった。「楽しかった」について、全員が同意しているという様子を、僕は感じることができなかった。たぶん、それはごく自然のことであって、そこから得た一つの教訓として、そこで「楽しかった」ことを押し付けてはならないんだな、ということだった。
そうなったとき、「学級」という場を、少なくとも自分がその場に対して関わる上で、どのような場になってほしいと願うのか、ということの考えを、少し改めることができた。学級という場を「チーム」とすると、苦しくなる場合がある。それよりか、「コミュニティ」というほうがいいのかも知れない、と。
ある人が言っていたところによると、「チーム」は同じ目標を持った人どうしの集まりで、共通目標に対してアクションを起こすことの共通理解を持っている、と。一方の「グループ」は、たんなる人の集合体でしかない、と。「コミュニティ」は、その間くらいにあって、互いの目的がバラバラであっても、誰かが困ったりヘルプを要したりする場合、あるいは誰かの目的達成に協力したいと思った時、構成員が相互に協力し合えるような関係性のことを指す、という主張だった。
作中の35人は、考えてみればごく当たり前なのだが、やっぱり違った存在だった。だからこそ、そこを画一に捉えるよりも、互いが互いを、必要に応じて支えたり離れたりするくらいのほうがいいのかもしれない、と思った。きっと14歳という年齢には、その感度が十分に備わっている。
そこに対して関わりを持つには、僕はまだ精進が足りない。僕の申し訳なさは、そんなところから湧き上がってくるのだった。
きっとこの作品は、DVDになることはないだろう。もう一回、見ておきたいなぁ。