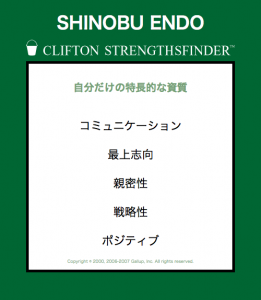コミュニケーションのあり方っていろいろだと思う。
言語コミュニケーション教育を理念と実践のうえで研究をしていくのが私のSFCで追い続けているテーマであるが、言語コミュニケーションだけがすべてではない。ただ、コミュニケーションを専門としておきながら、言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションの比率を忘れていた。そうだ、講義ノートを見返せば、7:93だった。
僕の持論は、義務教育の英語という教科の枠組みの中で、いかなる言語の使用においても基盤になる「普遍的コミュニケーション能力」を育む必要があり、その「普遍的コミュニケーション能力」とは、他者とかかわり合いを持とうとする態度、コミュニケーションに対する楽しさや難しさの認識、そしてその難しさを乗り越えてできるだけコンフリクトを起こさないための最低限度のワザだと思う。もちろん、性格が内気だったり人見知りだったりする人もいるけれど、そうした人でも一定レベルをクリアできるだけのワザがあってもいいはずだ。それを身につけてこそ、英語という教科枠組みが存在しうる価値だ、と。それが僕の研究です。
んでも、コミュニケーションのあり方っていろいろだと思う。
何が言いたかったのかというとですね、先日こんなことがあったわけです。10/8のことでした。
双葉町の子どもと遊ぼう #smiles_futaba だん。今日は、小学校高学年女子からメガネさんと呼ばれ続けながら、彼女たちのケリとパンチを受けまくるサンドバック状態。おかげで体が痛い。
もはやですね。今日、子どもたちと遊んでサンドバッグ状態に蹴られまくったことはですね、就職活動とか勉強会とかよりも僕にとって重要なことだったと思うのですよ。蹴られまくった末に「ストレス発散させてくれてありがとう」と一礼した少女は忘れられぬ。また行く。 #smiles_futaba
福島県双葉町は、福島第一原発を有する町。そこから避難してきた方々がいらっしゃるのが、旧騎西高校。そこでの子どもと遊ぶ活動・3度目の訪問です。その日、運動会などが実施されたり、いろんなプログラムが実施されていて、子どもがそもそも少ない避難所から更に子どもが少なくなっていました。それでも、女の子4人ほどがやってきて遊んでくれました。
しかしねぇ、その子ら”凶暴”なんだわ(笑)。あ、あくまで冗談として言っているのですよ。やっぱり、見知らぬ大人がたくさんいて、しかも男の人と接触するのもなかなか無いとなると、小学校高学年だったその子たちは、男の人に対して多少たりとも乱暴な言動をしてしまうのかなぁ、なんて思うわけですが。
とにかく、その子どもらが僕を蹴ってくる。どんどん蹴ってくる。痛い。膝をいためてめっちゃくちゃ痛がった演技をしたりして笑いながらキレるそぶりを見せると、なんだかそれが面白かったみたいでした。「男の子も蹴っ飛ばしてるよ」「そりゃ男子がかわいそうじゃないか」「いいんだもん」そんな会話から少しずつ打ち解けてきた感じでもあった遊びの活動。途中から、携帯ゲームを取り出して大人に対して挑戦してきたり、パソコンに熱中したり、などしていました。
物静かな女の子が一人。その子がどうやら折り紙が上手いらしく、「ねぇねぇ折り紙の折り方教えてくれよ」と言って、小鳥の折り方を教わったあたりから、物静かな女の子は実は物静かじゃなかったということが分かりはじめました。しかも、次に折りはじめた折り紙は途中で失敗し、「あ、折り方間違えちゃった、あれ?」みたいな感じになっていたわけで。その辺から、むしろその物静かな女の子も僕のことを蹴っ飛ばしてくる一味になりました。
他のメンバーの方が、ハロウィン仕様の折り紙工作を用意してきてくれました。画用紙のバッグに、パンプキンとこうもりの折り紙を貼る、というもの。僕もそれに参加し、パンプキンとコウモリを折りました。それを、最初に僕の膝を蹴った女の子が全部パクっていき、自分のものにして貼付けていきました。「え、俺のでいいの?」みたいな感じでしたが、快くもらってくれました。
僕はその日、メガネと呼ばれながら、ひたすら女の子たちのキックをうけまくりました。これ、普通なら度が過ぎるから、とブチギレるところですが、その日の僕は、その攻撃を上手くかわしながら、キックを受けまくりました。キックをよけながら、「ストレスたまってるんだねぇ」「子どももなかなか大変だよね、分かるよその気持ち」などとチャチャを入れつつ戯れていると、キックしながら女の子は爆笑し、そしてキックは更にエスカレートします。でもそれは、僕が本気で憎まれている状況では決して起きないことだなぁ、と後から振り返ると思います。その証拠に、キックをしながらいろんな話をしました。クラスの男子の話、学級担任があまり好きではないこと。僕は教員になりたい、という話をすると、じゃぁメガネが先生になってよ、と言われながらやっぱりキックを受ける。
もうすぐ店じまいの時、「今度いつ来るの?」という質問と「ストレス発散させてくれてどうもありがとう」という一礼。この時、僕はこういうのもアリなんだな、と思いました。避難した子どもはストレスを溜めているから思いっきり遊んだり乱暴になったりする、とよく言われますが、いや避難している子どもだろうが普通にその辺にいる子どもだろうが、少し年が若めの大人に攻撃しかけてくるのは普通だろう、と思います。別に僕は、色眼鏡をかけて見ていたから受け入れたのではありません。ただ、自分なりのスタンスで、子どもと接していただけです。もちろん、蹴っ飛ばされるのは痛いしいやだから、怒ることはできました。でも、それで萎縮させて関係を破綻させることを僕はおそれる。だから、通常の人と人との関係の中で、僕は彼女たちのキックを甘んじて受け、それに対して、彼女たちの力が抜けるような突っ込みを入れていった、ということなだけです。それが結果的に、メガネさんとして構ってもらえることにつながったのが僕にとってはすごく安心できる結果でした。
ことばだけがコミュニケーションじゃない。怒ったり褒めたりすること以外にも、信頼関係を気付く方法はいくらでもある。まさかキックでコミュニケーションが紡ぎだされるとは思わなかったけれど、それもまた一つの接し方だと思います。